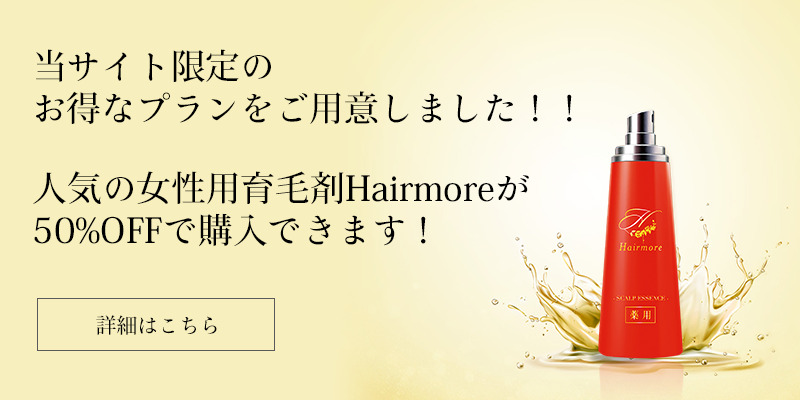毛は美容にかかすことのできないものであることは誰でも知っていると思います。
ヘアースタイル一つが、その日との顔たちを決めているといっても過言ではありません。
では毛は何のために存在し、どのようにして成り立っているのかを知っている人はあまりいないと思います。
髪が美しく見えるかどうかは、皮膚の外に出ている毛の部分の性質によって決まります。
なので私たち女性は環境の中で何が毛を傷めるかをよく知っておかなければ美しい髪の毛を保つことはできません。
そこでこの記事では、健康的で美しい髪の毛を維持するために、髪の毛の成り立ちや構造などの知り、日々のヘアケアに生かせるように解説していきますので、是非参考にしてください!
毛の構造
毛はケラチンと呼ばれる硫黄を含むタンパク質が主成分で、角層、爪と同じ成分でできています。
ただ毛と爪のケラチンは硬ケラチンと呼ばれ、角層の軟ケラチンと区別されています。
角層の軟ケラチンはほぐれやすくてばらばらになりやすいですが、硬ケラチンはお互いにしっかり結びついていて、一定の形をとり、その形は崩れにくいです。
毛では細長いタンパク質の繊維がその長軸の方向に平行に並んでいて、その繊維が束ねられていて毛の形を作っているのです。
つまり線香の束のような成り立ちをしているのが、毛と考えれば良いのです。そのためどの部分の断面を見ても、一定の繊維はその断面で決まった位置を占めています。
そうして線香では周りが紙でくるまれてバラバラにならないようになっていますが、毛では髪同士の繊維がお互いに手を出して、握りあって、一定の形を保っています。
毛と水分
縮れた毛でも、水に浸してくしでとくと、まっすぐにのばされ、その状態で短時間に乾かすと、しばらくまっすぐのままでいます。
パーマをかけた毛でも同じ傾向があり、入浴から出てきた人を見ると、今までの毛のちぢれが取れている人を見かけるのはそのためです。
このように、縮れた毛でも、水でぬらすと一時的にまっすぐに直すことができるのです。
毛は水分を吸いやすい
なぜ濡らすと毛を伸ばしやすいのかというと、毛は角質と同じように水分を吸いやすいものの一つです。
水分のない毛はカサカサしており、髪油、ヘアークリームなどを使うのも髪の毛に一定の水分量を保たせて、柔らか味を持たせるためです。ボディークリームなどが皮膚に潤いを与えるのと同じ要領です。
それでは毛はどれぐらいの水分を吸収することができるのかというと、乾燥した毛の重さの35%の水分を吸収すると飽和するといわれています。
この時は毛は膨張して長軸の方向に1~4%、横軸では14%ののびがあります。
しかもこのように水分を含んだ毛は、弾力に富んでいて、引っ張ると乾燥した毛の1.5~1.75倍の長さにまで伸びます。
毛の栄養
毛はタンパク質でできていると前述してきましたが、皮膚と全く同じもので、ケラチンが主成分となっているということも解説してきました。
そのため動物性タンパク質をとることが大切なのです。例えば、牛肉、卵、鶏肉などが、タンパク質を多く含み、毛のために良いといわれています。
毛の栄養の目的
毛に栄養が必要なのには2つの目的があります。
・美しい丈夫な毛を作り上げること
・毛と毛乳頭の結びつきを良くして、抜け難しくすること
この2つの働きは密接な関係に合って、皮膚にしっかりついている抜けにくい毛は、丈夫で美しい毛を作り上げています。
しかしこういった毛も、何の手入れもしないで放置しておくと、もろくなる恐れがあります。そのため、同時に毛を丈夫に保つように務めることも大切です。
つまり、毛の栄養を取るだけで十分というわけではなく、毛を上部に保つために使われるのが整髪剤です。
しかしこの中で解説している「毛の栄養」の意味は、毛を整えるもののことで、毛の発育に必要なものは食物などを通して取らなければいけない、これが本当の毛の栄養です。
毛とビタミン
毛は皮膚と同じ成り立ちを持っています。そのため、動物性たんぱく質が、この2つの栄誉上欠かすことのできないものだると同じく、皮膚に必要なビタミンの存在は、毛にとっても重要です。
ビタミンAが不足すると、皮膚がカサカサしてくるように、毛ももろく弱いものになっていきます。そのうえ角層が厚くなって出口をふさぐために、毛の伸びも妨げられます。
ビタミンDは毛の発育を良くします。元々このビタミンは食物として取らなくても、日光に当たると皮膚で自然にできるものがあります。
例えば夏に、海水浴にいって日焼けすると脚の毛が目立ってくるという経験をしたことがあると思います。
それは日光で皮膚の血液循環が良くなることにも関係していますが、ビタミンDがたくさん作られ、毛の伸びが良く、また毛の太さも増してくるためであります。
秋になって、強い日光に当たる機会が多くなると、身体のムダ毛も増える可能性もありますので、女性にとっては厄介に感じるかもしれませんが、髪の毛の成長には欠かせない栄養素です。
毛の色
毛にはいろいろな色があります。日本人は黒色が主体になっていますが、ときどき日本人の間にも青眼で金髪の子供が生まれてくる「白子」といわれる病気で生まれつき毛の色を作る働きができない身体の子もいます。
メラニン
毛の黒色はメラニンと呼ばれる物質のためで、金髪ではメラニンが無くなっていることが分かります。
毛のメラニンは、毛母の色素細胞で作られます。
それが毛の皮質に含まれているのでありますが、メラニンがそこに入っているのではなくて、メラニンを含んだ細胞が、そのまま押し上げられて皮質をつくるので、皮質にメラニンが残るのであります。
色素細胞にメラニンを作る力が無くなると白髪が出てきます。
メラニンの配合量で黒さが決まる
メラニンが微細な顆粒として毛に一様に分布されているものでは暗い感じが強いです。
もう一つの毛の色との関係で重視されているものに鉄があります。
赤毛に含まれているのですが、他の色の毛にはほとんど鉄の存在は認められません。この鉄は毛の中でメラニンと分かれて存在しています。
こう考えていくと、毛の色にも様々な問題があります。なかには毛の色で女性の性格がわかるともいわれており、赤毛は遊び上手といわれています。
メラニンの分泌量は加齢とともに減少していく
よく歳をとると白髪が生えてくるといわれていますが、あながち間違ってはいません。
実は髪の毛に色を付けるメラニンは、歳をとるにつれてその分泌量が減少し、加齢とともに白髪が多くなってくるのです。
なので女性の方で白髪に悩んでいる方は40代~60代の方が多いのがそのためです。
中では若いころから白髪に悩んでいる方がいますが、そのような方は何らかの原因でメラニンが減少しているのですが詳しい原因については詳しくはわかっていません。
髪の毛の構造を知って適切なケアを
いかがでしたでしょうか?この記事では、毛の構造や成り立ち、色の秘密などについて解説してきました。
髪の毛ができるのには様々な過程が存在し、いわば活きているということです。
元気な髪の毛を生成するためには、毛の元となる栄養素をしっかりと摂取する必要があります。
タンパク質やビタミンなどの栄養素を含む食物をできるだけバランスよく摂取するようにしましょう。
栄養をしっかり取り、毎日ヘアケアをしっかりしていれば、元気で艶のある髪の毛が維持できますので、是非実践していきましょう!